所長メッセージ

![]()
学校はこの30年余り、ちょうど1世代をかけて大きく変化してきました。
それを実現させてきたのは、学校づくりのプロセスの変化だと言えます。
教職員、PTA、地域住民、児童生徒の意見や要望を聞くだけでなく、設置者や専門家らとともに話し合いやワークショップを重ねる学校づくりが定着してきました。
今日、社会の変革に対して、新しい教育目標、学校像を描き、その実現を図ることが課題となっています。
そのためには、それぞれが想いを語り合い、課題を共有し、目指すものを明確にするプロセスが一層重要度を増しています。
また、それを通じて当事者意識が育ち、完成後の教育実践や学校運営、学校支援等に積極的な工夫が生まれ、ソフト・ハードを合わせて生き生きとした学校になるのです。 教育改革をめざす学習空間、生涯学習拠点として地域施設との連携や複合化、地球環境に優しいエコスクール、地域を元気にする木の学校、地域ぐるみの小中一貫教育等、新しい課題は目白押しです。これらに応える学校づくりは、夢や想いを皆で語ることでなければなりません。
安全・健康・地球環境問題等、守りの課題もしっかり受け止めながら、教育のあり方、学校の役割、地域の将来を皆で考える絶好の機会として、参加による学校づくりのプロセスをとらえていく必要があります。
それはさらに学校を中心として、生涯学習、社会福祉の領域まで統合し、クォリティ・オブ・ライフという目標につながります。安全安心に支えられ、日常生活の幸せ、楽しさ、生きがいが感じられる「生活の質」の追求と実現につなげていくことが大切です。
所長 長澤 悟
![]()
 |
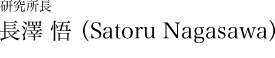 東洋大学名誉教授。工学博士。 国立教育政策研究所文教施設研究センター客員研究員。 東京大学大学院博士課程修了。東京大学助手、日本大学工学部専任講師、助教授、教授、東洋大学理工学部教授を経て現職。 専門分野は建築計画(教育施設、地域施設、住宅等)、設計。 特に、教育方法の多様化に対応した学校建築計画、地域施設計画、計画・設計プロセス、住宅・地域づくり等に関する研究を進める。また、学校建築等の計画・設計について、教職員・PTA・住民・子どもたちが参加する計画プロセスを取りながら、新しい学校のあり方を提案している。 【 主な受賞歴 】 2010(府中市立府中小学校・府中中学校)、2008(坂井市立丸岡南中学校)、2006(昭和町立押原小学校)にて日本建築学会作品選奨 2000、日本建築学会賞[業績](福島県三春町の一連の学校計画) 1998、第18回福島県建築文化賞準賞(福島県棚倉町立社川小学校) 1991、日本建築学会賞[作品](浪合学校) 【 主な著書 】 「建築設計資料105学校3」、建築思潮研究所、2006 「スクール・リボリューション」、彰国社、2001 「やればできる学校革命」、日本評論社、1998 |



